1.分析の目的
5/8(日)に開催された早慶戦ゴルフコンペは残念ながら団体戦で24打差の敗北を喫した。撮影班だった筆者はティーで全選手のショット見たが、結果程の差は感じられなかった。では、何がこれだけの差を生んだのだろうか?
次回リベンジへの布石として、スコア分析を行ってみたい。 |
2.分析対象
団体戦における各校第10位のグロスは早稲田100/慶応93だった。
しかし、選手には例外なく好不調の波があるので、10+α人のスコアで分析してみたい。慶応からは今回20打改善の例が報告されたが、これは数少ない例であり、一般的には約±5打が好不調の波だろう。
すると、このときグロス早稲田105/慶応98までの選手が団体戦にカウントされる可能性が高かった選手と考えられ、その順位は早稲田第17位/慶応第14位となる。その中間をとり、各校15位までの選手のスコアを対象とすることにした。(但し3項チーム分析は全選手が対象) |
3.チーム分析(スコア分布)
グラフ1:スコア分布
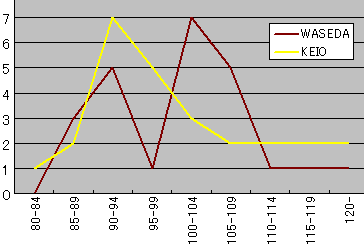 |
グラフ1は早稲田、慶応それぞれのスコア別選手の分布図である。
早稲田の敗因はこれまでに選手層の薄さと言われて来たが、改めてそれを裏付ける結果となった。
慶応は90台前半を中心として、前後ムラの無い選手構成となっている。対して、早稲田は上位(99以下)と下位(100以上)がクッキリと分かれている。
上位陣は慶応に対して善戦していることから、団体戦に勝利する為には上位陣に次ぐ選手の上達が不可欠と考えられる。 |
4.上位15名のスコア分析
表1:上位15名のスコア平均
|
早稲田 |
慶応 |
| OUT |
IN |
GROS |
OUT |
IN |
GROS |
| 平均 |
47.87 |
47.53 |
95.40 |
45.80 |
46.40 |
92.20 |
| 差 |
▲2.07 |
▲1.13 |
▲3.20 |
- |
- |
- |
|
表1は各校上位15名の平均スコアである。
OUT、INともに早稲田が慶応のスコアに負けており、まずはその力の差を認めざるを得ない。しかしながら、ここで注目したい点は、OUT=約2打、IN=約1打とその打数差に約1打の違いがあることである。
トータル距離は、OUT=3,280yard、IN=3,315yardとほぼ同じであるが、各ホールの難度を示すHDCPの合計数は、OUT=81、IN=90と若干INが易しくなっている。もしかすると、早稲田は難易度の高いホールを苦手としているのではないだろうか?
この点に着目して、次項ではホール毎の分析を行ってみたい。 |
5. 各ホールのスコア分析
各ホールの各校平均スコアは表2の通りとなっている。団体戦では大差が付いたが、早稲田が平均スコアで上回るホールもある。スコア差こそあるが、早稲田は決して全てに劣っていたわけではない。
表2:各ホールの平均スコア
| HOLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| PAR |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
3 |
4 |
| HDCP |
11 |
17 |
7 |
3 |
13 |
5 |
9 |
15 |
1 |
| 早稲田 |
5.60 |
3.87 |
5.33 |
6.00 |
4.53 |
6.20 |
6.67 |
3.93 |
5.73 |
| 慶応 |
5.40 |
3.93 |
5.13 |
5.47 |
4.40 |
5.80 |
6.47 |
3.93 |
5.27 |
| スコア差 |
▲0.20 |
0.07 |
▲0.20 |
▲0.53 |
▲0.13 |
▲0.40 |
▲0.20 |
0.00 |
▲0.47 |
| HOLE |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| PAR |
3 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
| HDCP |
16 |
4 |
14 |
8 |
2 |
10 |
6 |
18 |
12 |
| 早稲田 |
4.00 |
5.80 |
4.87 |
6.47 |
5.73 |
5.87 |
5.60 |
4.00 |
5.20 |
| 慶応 |
4.33 |
5.67 |
5.00 |
5.87 |
5.13 |
5.87 |
5.60 |
3.93 |
5.00 |
| スコア差 |
0.33 |
▲0.13 |
0.13 |
▲0.60 |
▲0.60 |
0.00 |
0.00 |
▲0.07 |
▲0.20 |
|
また、グラフ2は各ホールのスコア差とHDCPをグラフにしたものである。すると、一部(IN後半)を除いて、HDCPとスコア差は同じような動きをしていることが分る。
グラフ2:各ホールのHDCPとスコア差
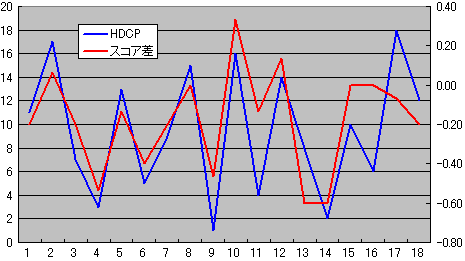 |
前項にて推測した内容はこれで証明されたこととなる。即ち、早稲田は難易度の高いホールを苦手とする傾向にある。
表3:ホール種別毎平均スコア
|
PAR3 |
PAR4 |
PAR5 |
| 早稲田平均 |
3.95 |
5.44 |
6.30 |
| 慶応平均 |
4.03 |
5.21 |
6.00 |
| スコア差 |
0.08 |
▲0.23 |
▲0.30 |
|
同様の傾向はショート、ミドル、ロングホールそれぞれの平均スコアからも得られる。(表3)
早稲田はショートホールを得意とし、平均スコアは慶応を上回る。ちなみに、柿澤先輩のホールインワンを-2打と考慮すると、0.03打の効果であり、それを差し引いても0.05打慶応を上回っている。尚、ショートホールは難易度が低い4ホール(HDCP15-18)に設定されている。
逆にPAR4、PAR5では慶応に差を付けられる結果となっている。PAR5のHDCPは5,8-10と、必ずしも難易度が高く設定されているわけではないこと、またPAR4よりさらに慶応に差を付けられていることから、早稲田はPAR5をより苦手としていると言える。ただし、この結果から飛距離が劣ると考えるべきではなく、慶応の方が、難易度が高いホールや距離の長いホールをうまく攻めた(試合巧者だった)と考えるべきだろう。 |
6. まとめ
以上の分析より次回リベンジへのカギは次の通りと考える。
- 「上位陣に次ぐ選手の上達が不可欠」
団体戦ではムラのない選手構成が勝利への重要なカギとなる。早稲田は選手層にムラがあり、上位陣と下位陣のスコアに開きがある。今回グロス100台を中心とした選手の躍進が、次回リベンジのカギであり、幸いにも早稲田には人材が豊富に揃っている。
- 「コースマネージメントが重要」
慶応とのスコア差は単にボールを打つという技術的なものとは言い切れない。なぜならPAR3の平均スコアでは早稲田が勝っているからだ。ここでは、慶応との差はコースマネージメントだと結論付けたい。同じホールはないし、同じ一打はない。それぞれのホールとその時に置かれた状況を把握し、それに合った攻め方をしているか?選手各位が考えてみる必要があるのではないだろうか。
どうすればコースマネージメントが身につくかについては、諸先輩方々にお願いしたい。 |
7. 最後に
今回の分析結果はコースマネージメントの重要性を改めて気付かせてくれる、大変興味深いものだった。
筆者もまさにグロス100前後で、ここ数年は伸び悩んでいる。まさにこの分析結果は自分自身のことを指しているようで、大変むずがゆい。今後はどう攻めるかを意識して1つ上を目指してゆきたい。
また、今回上位15位までを分析対象としたが団体戦の性格上、全選手の頑張りが不可欠であることは言うまでもない。熱のこもった素晴らしいプレーは、チームに活力を与える。次回全員の力でリベンジを果すことを願ってやみません。 |
ご意見やご助言はどうぞ掲示板へ投稿してください。異論、反論もちろん大歓迎です。 |